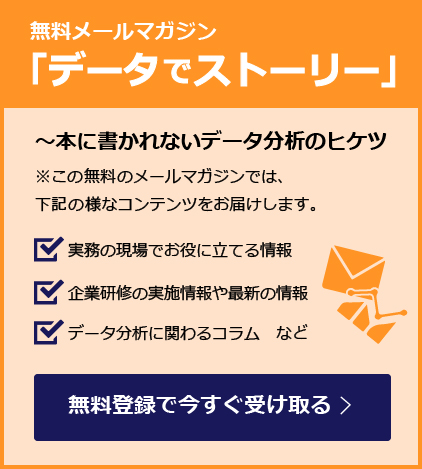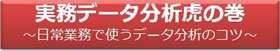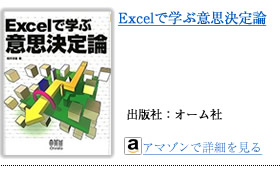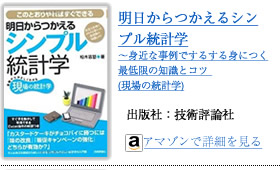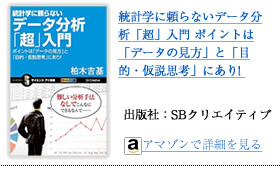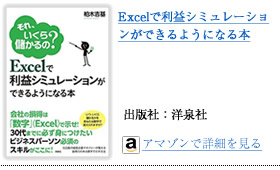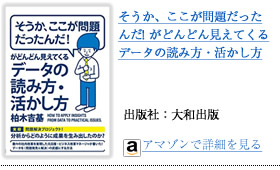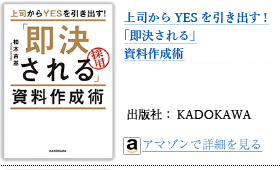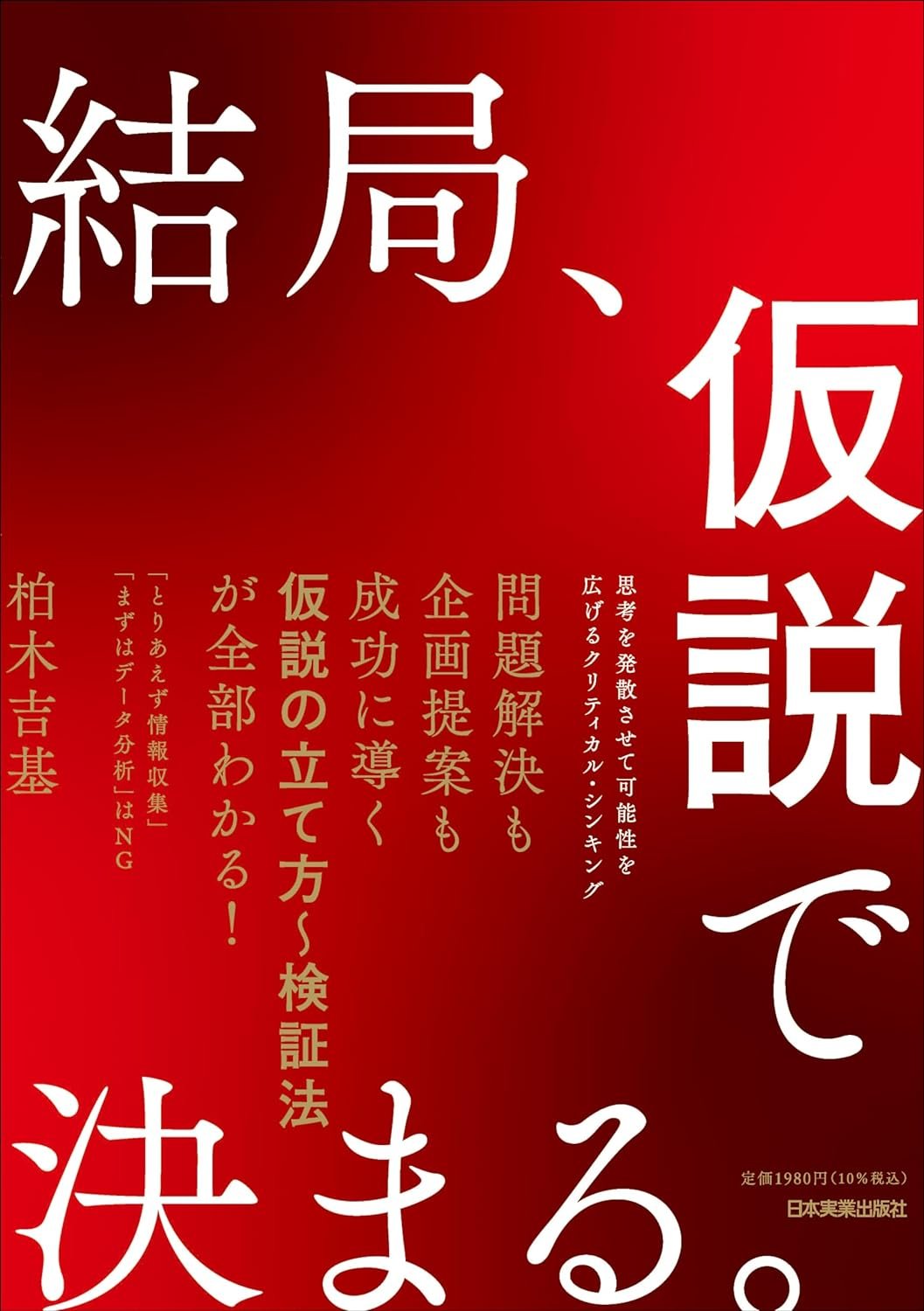前回大好評であった「データ分析デザイン」のセミナー再開催!
2025年年明けの1月24日に、前回大好評であった「データ分析デザイン」のショートセミナーを再度開催致します。
業務や課題解決のために、データ活用を実現するための具体的な設計図作りを「データ分析デザイン」と呼び、その組み立て方、考え方を2時間でお伝えします。
https://event.shoeisha.jp/bza/datadesign-online
データやデータ分析を活用するには、「データから情報を読み出す」だけでは全く歯が立ちません。
その前の目的(ゴール)に始まり、やりたいこと、引き出したい内容、適切なデータの選択など、作業の下地を具体的に考えておく必要があります。
一方で、そのために何をどう考え、どんな注意点があるのかを学んだり体験する機会はほとんどありません。
これが「データを活用できていない」最大の理由である、とも言えます。
そのような重要なポイントをオンラインで2時間(ライブで行います)で学べる絶好の機会です。
是非、ご参加ご検討下さい。