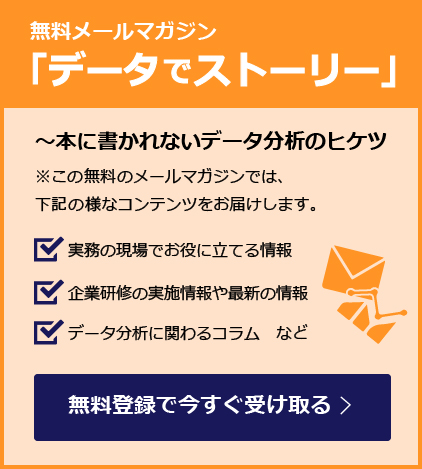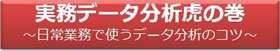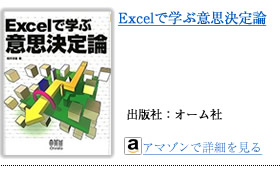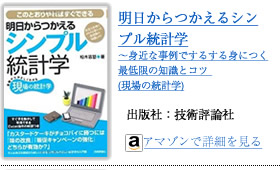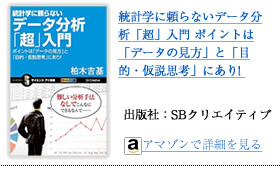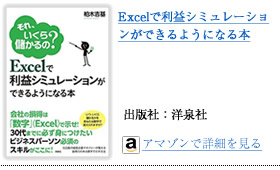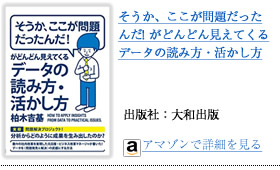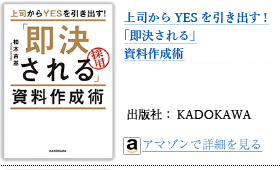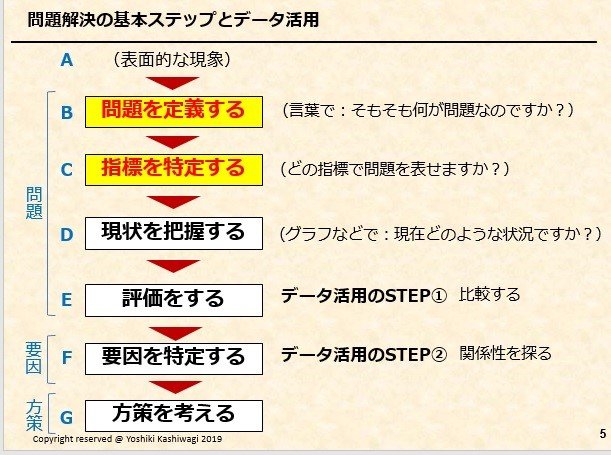「データ分析する」って何をすることか言えますか?
スーパーサイエンスハイスクールに指定されている徳島県立富岡西高校にて、「データ活用」の授業を行ってきました。
それまで全くデータ分析に関することをやったことがない(=先生方も教えたことが無い)というゼロベースで、「自らテーマを立てて、データを活用した研究を行う」プロジェクトを進めています。
グラフを自ら作ったことがない高校生に対して、「データ分析する」ってどういうことか、ここから問いかけてみました。
最初に生徒に見せたものがこちらです。
「皆さんは、この中のどこが”データ分析“に相当すると思いますか?複数ある場合にはその箱を手を付ける順番に並べてみてください」と言って10分間個人とグループで考えてもらいました。
いくつかのグループに発表してもらうと、それぞれ少しずつ違うものが出てきました。
(う~ん、やはり・・・・)
ここからの話は長くなるので割愛しますが、ここで伝えたかったことは、「データ分析」とはA~E全てを含むこと。
そして、その適切な順番は次の通りということです。
まずは、「データを活かす」ために何をどのような順番で進めていくのか、について学んでもらいました。
今回はこれを伝えて理解してもらうだけで精一杯でしたが、今後もこの授業を続けて行きます。
実は、この準備段階で、私なりに大きな気づきがありました。
それは自治体でのデータ利用においても共通して見られることでした(逆に、民間企業で遭遇することは少ないのです)。
「テーマ」と「問題・目的」の違い、がそれです。