
実務データ分析虎の巻Vol.105~データ活用スキル習得の第1歩
徳島県立富岡西高校(SSH指定校)の「データに基づいた研究」授業をSSH(スーパーサイエンスハイスクール)の中で実施しています。このプログラムの中では、それぞれの生徒が、自分のプロジェクト(地域に関連する提案や問題解決)をデータに基づいて行いながら、3年間を通じてそのスキルを身に着けていくものです。

徳島県立富岡西高校(SSH指定校)の「データに基づいた研究」授業をSSH(スーパーサイエンスハイスクール)の中で実施しています。このプログラムの中では、それぞれの生徒が、自分のプロジェクト(地域に関連する提案や問題解決)をデータに基づいて行いながら、3年間を通じてそのスキルを身に着けていくものです。
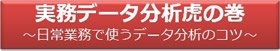
徳島県の県立高校で、高校生向けの授業を行っています。論理的に自分のプロジェクトや提案を作ることに取り組んでいますが、やはりデータをどこで使うのか、論理をどう組み立てるのかといった基礎は先生も含めて習ったことがなく、自己流でやると全然うまく行きません。個々のケースに向けた細かいテクニックやアドバイスはあるのですが、一般論としてまずは身に付けてほしいポイント(鉄則)を2つだけまとめたものがこちらです。
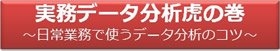
プロモーションやディスカウントなど、何かしらの効果を期待して行う様々な施策。
「一体効果はあったのか?」という基本的な疑問だけでなく、効果があることを前提に「いつ効果が発揮されたのか」を知りたいと思うこともあります。
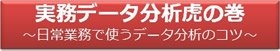
企業も自治体も最近の合言葉として「イノベーション」が花盛りです。ところが、「では御社の(地域の)イノベーションの状況を数値で見せてください。他より進んでいるのですか?遅れているのですか?一体、促進するってどのレベルがゴールなのですか?」と意地悪な、でも極めて基本的なことを聞いて答えが返ってきたケースが今のところありません。
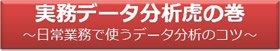
今流行りの「働き方改革」問題へのデータ活用の場面です。部署ごとの平均残業時間と、事務処理ミス件数との関係性をデータから見ようとしていました。こんな感じですね

私のキーワードは「データ活用」です。どんなに素晴らしいデータ分析をしても、自分の目的に対して適切に“活用”できない限り、データを使いこなしたとは言えません。
そして、この点で多くの人が行き詰っていることも事実です。

自分が考えたビジネスをデータで検証するための「アンケートの作成とその集計、分析」ですが、アンケートの質問次第で、結果の質が大きくブレます。
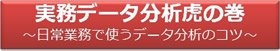
今回は、データ活用に共通して見られる「テーマ」と「問題・目的」の違いについて紹介します。
この違いとは、「データを活用する出発点」の違いと言っても良さそうです。
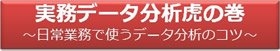
スーパーサイエンスハイスクールに指定されている徳島県立富岡西高校にて、「データ活用」の授業を行ってきました。それまで全くデータ分析に関することをやったことがない(=先生方も教えたことが無い)というゼロベースで、「自らテーマを立てて、データを活用した研究を行う」プロジェクトを進めています。

データ活用の基礎的なテクニックの一つが、1つだけでなく、2つの軸での評価です。ここで言う”軸“とは、「尺度」や「評価基準」と言い換えても良いかもしれません。