
実務データ分析虎の巻Vol.60(相関分析のコツ~“風が吹けば桶屋が儲かる”の相関は厳しい)
相関分析において致命的となる、2つの関係の”距離“について言及していないことが多く見られます。

相関分析において致命的となる、2つの関係の”距離“について言及していないことが多く見られます。

「業務でデータ分析する機会がない」という人がいるが、「じゃあ君これを分析してね」が降りて来るのを待っていると一生そんな機会は来ない。自分で機会を作るのです。「業務でデータ分析する機会がない」という人がいるが、「じゃあ君これを分析してね」が降りて来るのを待っていると一生そんな機会は来ない。自分で機会を作るのです。
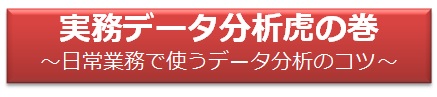
あなたの組織では、データ活用が「現状把握」にとどまっていませんか?その次はいきなり方策に飛んでいませんか?

そのような中、ワシントン大学のビジネススクールでクリティカルシンキングを教えている教授とコンタクトが取れ、授業内容の情報交換をしたところ、いくつかの大学院で共通して教えているテーマが「課題設定・定義」ということが分かってきました。

いくつもの業種にまたがるクライアント様のお手伝いをする中で、うわべだけでなく、本当の意味でデータ活用力、問題解決力、分析力を組織の力に変えたいと考えている人やチームは一体それ以外と何が違うのでしょう。
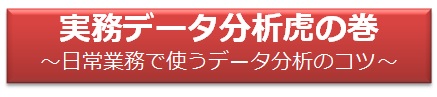
例えば、「標準偏差」。これを理解したところで、いつどう活用したら良いか、パッと一例が浮かびますか?多分、浮かばない人が圧倒的でしょう。

2種類の指標の間の関係性を数式化する回帰分析(かいきぶんせき)と呼ばれるものがあります(これを単回帰分析と呼びます)。賢くビジネスに応用すれば、圧倒的な威力を発揮します。

分析結果の形や見せ方のテクニック(グラフやデザイン、レイアウトなど)は別なトピックとして数多ありますが、分析結果そのものが本質に答えられていなければ、どんなにきれいなグラフでも中身が相手に伝わりません。

データ分析結果からは、そこに至るプロセスや分析者が作業中に取った個別の判断内容が見えません。
そんな結果だけをみて判断を求められるマネージャには2点、大きな落とし穴があるのです。

部門間の業務連携が進んだ理由とは? 中部地方の中小メーカーをサポートしています。 これまで、営業部門が販売実績のあった製品や顧客情報だけを管理していたのですが、どうしても既存ビジネス維持の範囲...